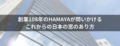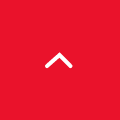2025年:激動の住宅市場、その光と影
2025年、日本の新築住宅市場は、かつてないほどの激動に見舞われています。その中心にあるのは、4月1日に施行された「脱炭素大改正」、すなわち建築物省エネ法改正による省エネ基準適合義務化です。この新たな規制が、市場に短期的な「駆け込み需要」と、それに続く「反動減」という劇的な波紋を広げました。
政策が描く市場の軌跡
法改正を目前に控えた3月、全国の新設住宅着工戸数は8万9432戸と、前年同月比39.1%増という驚異的な伸びを記録しました 。これは、多くの事業者が義務化前の着工を急いだ結果であり、一時的な市場の活況を演出しました。しかし、その反動は想像以上に大きく、4月以降は着工戸数が急減。特に5月は4万3237戸と、前年同月比34.4%減という大幅な落ち込みを見せ、1963年1月以来62年ぶりの低水準にまで沈みました 。6月も減少傾向は続いたものの、5万5956戸と減少率は15.6%に緩和され、市場の底打ちの兆候も示唆されています 。この一連の動きは、政策変更が市場の行動をいかに大きく左右するかを示す、まさに教科書的な事例と言えるでしょう。
各住宅タイプの明暗
個別の住宅タイプに目を向けると、その動向はさらに複雑です。
注文住宅(持家)は、厳しい状況が続いています。1月は前年同月比8.6%減の1万3525戸 、5月には民間資金による持家が31.8%減となるなど 、減少傾向が顕著です。資材価格の高騰、特に「ウッドショック」の継続 や金利動向、そして若年層の住宅取得意欲の低下 が、このセグメントの足かせとなっています。省エネ基準適合義務化による追加コストも、購入者の負担増につながっています 。
分譲戸建てもまた、苦戦を強いられています。1月は8715戸で27ヶ月連続の減少 、5月も29.9%減と大幅に落ち込みました 。2024年通年で分譲マンションよりも減少幅が大きかった傾向は2025年も継続しており 、資材価格高騰や土地価格の上昇が、購買意欲を減退させている主な要因です 。
一方で、**木造アパート(貸家の一部)**は、市場全体の低迷期にあっても相対的な堅調さを見せています。1月は2万4387戸で前年同月比1.2%減 、6月も2万4289戸で14.0%減となりましたが 、その背景には、木造住宅が他の構造に比べて建築コストが安価であること 、工期が短いこと、そして投資家からの安定した需要 があります。相続税対策や高利回りといった投資メリットが、この分野の需要を支えていると見られます 。
非木造構造については、直接的な月次統計は限られますが、鉄骨やセメント・コンクリートといった主要資材の価格高騰が、着工を抑制する大きな要因となっています。例えば、東京地区の生コンクリート価格は4月から14%上昇しました 。これらのコスト増と、省エネ基準適合義務化による追加負担が重なり、大規模建築物の着工にも影響を与えています 。
複合する課題と未来への視点
2025年の住宅市場を形成する要因は、省エネ基準適合義務化だけではありません。建設資材価格の高止まりは、ウッドショックやアイアンショックの継続、そして歴史的な円安によってさらに加速しています 。建設業界は慢性的な人手不足に直面しており、2024年の時間外労働規制に加え、2025年の新基準対応による業務量増加が、この問題を一層深刻化させています 。さらに、人口減少、少子高齢化、若年層の住宅取得意欲低下、賃貸志向の高まりといった構造的要因が、市場全体の縮小傾向を加速させています 。
今後の市場見通しとしては、2025年度通年の着工戸数は、前年度比で減少すると予測されており、78.0万戸から79.0万戸の範囲が示されています 。中長期的には、野村総合研究所の予測では2040年度には61万戸まで減少するとの見通しもあり 、市場の構造的縮小は避けられない現実として認識されています。
このような状況下で、住宅事業者には、省エネ基準適合への効率的な対応、建設コスト上昇への対策、人手不足の解消に向けた業務効率化と人材確保、そして変化する消費者ニーズへの適応が喫緊の課題として求められます。2025年の激動は、日本の住宅市場が新たな時代へと移行する過渡期であることを示唆しているのかもしれません。